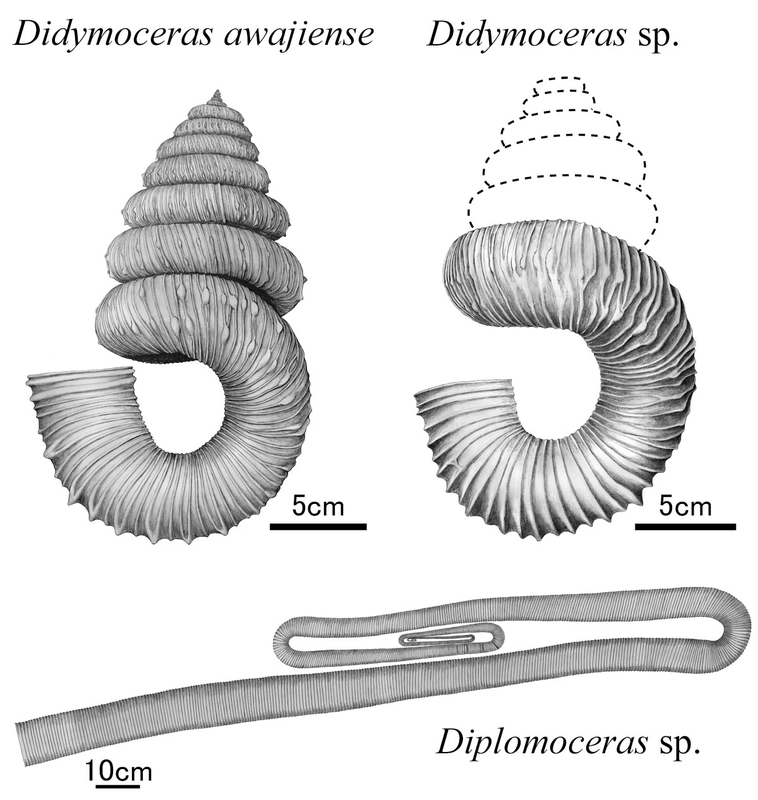↑Skeletal reconstruction of famous Smithsonian trikes.
Top, Triceratops horridus USNM 2100;
bottom, Triceratops sp. USNM 4842.
Scale bar is 1m.
スミソニアン――本ブログの読者にはたぶんUSNMと言った方が通りがよい――の恐竜展示の歴史は当然古く、化石戦争の戦後処理を担わされてからかれこれ100年以上に渡っている。そんなUSNMの恐竜ホールがリニューアル工事に入って5年が過ぎ、今夏ついに再公開されるわけである。
かつてのUSNMを飾っていた輝かしい復元骨格の数々――これまでも本ブログで取り上げてきたし、今後も取り上げるはずだ――はすべて実物からキャストへ置き換えられ、最新の技術で新たなポーズに組み直されたわけだが、その中でひっそりと「息を引き取った」マウントがある。お披露目から114年、紆余曲折がありながらもUSNMの「顔」として閉鎖された恐竜ホールの留守さえ守ってきた“ハッチャー”――トリケラトプスの合成復元骨格は、“合衆国のティラノサウルス・レックス”――USNMに50年間の期限でリースされたMOR 555に我が身を捧げたのである。
マーシュ麾下の最強の化石ハンターであったジョン・ベル・ハッチャーは“長角バイソン”を皮切りに、ほぼ全ての種のホロタイプを含むあきれるほど大量のトリケラトプスの化石を19世紀最後の10数年で発見したのだが、そういうわけで化石戦争がコープとマーシュの死で幕を閉じた時、トリケラトプスの化石はマーシュの拠点であったイェール大学ピーボディ博物館(YPM)にはとても収まりきらない量になっていた。かくして相当数の標本(ほとんどはジャケットも外されていなかった)がYPMからUSNMへと移管されたのだが、その中にはマーシュが生前記載・図示した標本も含まれていたわけである。
トリケラトプスの化石といえば今も昔も頭骨ばかりのイメージが強い(実際その通りではある)が、実のところ“ケラトプス”・ホリドゥスの原記載から2年後の1891年には、足を除く全身各部の代表的な要素が(“鎧”と共に)記載・図示されていた。その中にあったのが後のUSNM 4842――“ハッチャー”の主要部分を占める、かなり大きなおとなの部分骨格であった。
なんだかんだで(椎骨のカウントなど、謎は多かったのだが)それなりの要素が集まっていたこともあり、1896年にはマーシュによる北米産恐竜類の総括の中でトリケラトプス・プロルススの骨格の復元が試みられることとなった。この復元は(最初の復元の試みでありながら)いまだにトリケラトプスの復元イメージを支配しているという代物であり、そして究極的にはUSNMのトリケラトプスの運命を支配するものでさえあった(そしてこの骨格図の体部の主要部分をUSNM 4842が占めていることは言うまでもない)。
アメリカの輝かしい(そして血塗られた――当時の大統領であったマッキンリーは会場内で銃撃されその後落命した)20世紀の幕開けを飾るパンアメリカン博覧会にブースを出展するにあたり、USNMがシンボル展示に選んだのがトリケラトプスの復元骨格――いうまでもなく世界初――であった。とはいえUSNMに移管されたトリケラトプスの標本の多くはジャケットの開封が追い付いていない状態であり、USNMのキュレーターであったフレデリック・ルーカスは「張り子」でこれを作り上げることにしたのである。
(実のところルーカスは古生物学者ではなかった――鳥類を得意とする腕利きの剥製士ではあったのだが化石を扱った経験はなく、従ってルーカスはマーシュの骨格図を単純に「立体化」することしかできなかったのである。)
かくしてマーシュの復元に基づくトリケラトプスの復元骨格「模型」は1901年の5月から11月までニューヨーク州はバッファローで公開され(模型とはいえ、これはハドロサウルスと“クラオサウルス”・アネクテンスに次ぐアメリカ3種目の恐竜の復元骨格であった)大好評となった(1901年に描かれたナイトの有名な復元画は明らかにこの骨格に基づいている)。これに気をよくしたUSNMは、本家博物館の地質分野の目玉として実骨のマウントを展示することとしたのである。
パンアメリカン博覧会では断念されたこの難題を任されたのがUSNMにやってきたばかりの若手――ハッチャーの下でクリーニングの修業を積んだギルモアであった。手始めに“クラオサウルス”・アネクテンスのホロタイプをウォールマウントとして送り出し、そしてトリケラトプスの山の中から目を付けたのがUSNM 4842――頭骨の断片やいくつかの椎骨、肋骨と四肢の大部分、そして見事な腰帯であった。
首から後ろの主要部分はUSNM 4842を核にすることで落ち着いた(欠損部はサイズのだいたい合いそうな他の実骨で埋め、間に合わない椎骨などは石膏模型があてがわれた)が、もうひとつ問題があった。この骨格の「顔」が欠けていたのである。ここでハッチャーが見出したのがUSNM 2100――吻を欠くもののほぼ変形のない、見事な頭骨であった(下顎は別個体のものである点に注意)。
ハッチャーの死から1年後の1905年、ギルモアとその相方であるノーマン・ロスの手によって「トリケラトプス・プロルススの復元骨格」が完成し、USNMの目玉展示となった(当時の新聞記事が熱気を教えてくれる)。その後もギルモアとロスの手によって続々と恐竜のマウントがホールを飾っていく中にあって、この骨格はUSNMの化石ホールの顔であり続けたのである。
(「張り子」の復元骨格模型はその後セントルイス万博を始め全米各地を巡回し、その後一旦スミソニアンの展示に復帰した。1907年にはこれと同型のものが大英自然史博物館で展示された(今日でも常設展示のままである)が、これがオリジナルの「張り子」そのものなのか、「張り子」のレプリカであるかははっきりしない。)
1907年になってようやく出版されたハッチャーの遺作である角竜のモノグラフ(もともとマーシュの死後ハッチャーが引き継いだ研究であった)でUSNM 4842とUSNM 2100は詳しく記載・図示され、特にUSNM 4842については貴重なトリケラトプスの体骨格ということもあってその後も様々な文献に図が転載されることとなった。80年代の後半になりポールがトリケラトプス・ホリドゥスの骨格図を描いた際にも、四肢と腰帯にはUSNM 4842があてがわれさえしたのである。
黄鉄鉱病でいよいよ限界に来ていたマウントは、1998年になってついに来館者のくしゃみのショックで腰帯が崩壊を始めた。USNM 4842はバックヤードへ勇退する一方USNM 2100はそのまま単体の展示として残留し、そしてこの骨格は最新技術のデモンストレーションを兼ねて全身を3Dスキャンされた。20GB“もの”データを元にこの骨格のプロポーション――USNM 2100はUSNM 4842と比べて一回り小さな個体であった――は矯正され(ついでに足にあてがわれていたエドモントサウルスも追い出された)、2001年に“ハッチャー”としてこの骨格は再デビューを飾ったのである。
USNMの黄金時代を飾った“ハッチャー”の功績は上に書いた通りであり、USNM 2100にせよUSNM 4842にせよ、その標本としての重要性はいまだに揺るがない。USNM 2100ほど変形の少ない成体の頭骨は他にほとんど知られていないし、USNM 4842ほどのサイズで体部の記載のある(それも変形のほぼみられない)トリケラトプスは他にないのである。
トリケラトプスの復元イメージを114年間担い続けてきた“ハッチャー”は、かくしてUSNMの恐竜ホールの顔役をティラノサウルスへ譲り、文字通り身を捧げることとなった。USNM 4842に基づくポールの骨格図もフィールドガイドの第二版から消えたが、それでもギルモアとロスが手塩にかけた標本たちはUSNMの収蔵庫で息づいている。
(USNM 4842の頭骨のうちまともに残っているのは上眼窩角だけであり、従って(上腕骨の形態からしてトロサウルス属ではなくトリケラトプス属なのはほぼ確実だが)USNM 4842の種を定めるのは難しい。USNM 4842のナンバーを振られた断片の中には明らかにエドモントサウルスの上顎骨が紛れ込んだりしているのだが、一方でどうも鼻角らしいものも見受けられる。何となく腹側から撮影したように見え、だとするとホリドゥス的な小さな鼻角のようにも見えるのだが、さてどうだろう。)